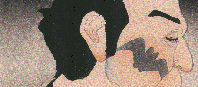谷崎論
〜手紙の女〜
(『埼玉大学紀要 教養学部』第31巻 第1号 1995年)
「蝙蝠安」山村耕花画大正6年
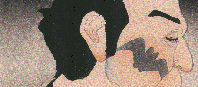
『刺青』について −手紙の女−
八木 惠子
1
谷崎潤一郎の短編小説「刺青」(明治四十三年十一月 初出第二次「新思潮」三号)において、辰巳の芸妓が刺青師清吉に宛てた手紙には二つの用件が書いてある。
一つは、使いの娘に託した羽織りの裏地に「絵模様を画いて」もらいたい旨。いま一つは、当の娘が「近々に私の妹分として御座敷へ出る筈故、私のことも忘れずにこの娘も引き立てゝやつて下さい」というものである。
だが、清吉は辰巳の芸妓の「羽織り」の裏に絵を画くかわりに、芸妓の妹分の娘の肌に「女郎蜘蛛」の刺青を刺った。「女郎蜘蛛」を背負って帰った娘のその後の運命は、思うだに案じられる。凄艶な女に変貌した娘を目の当たりにして、芸妓の驚愕はいかばかりであったろう。「親方、なにもここまで引き立ててくれなくたっても」と、言ったかどうかは解らないが、わが「羽織り」の「裏」ではなく、妹分の生身の背肌に刺られた「女郎蜘蛛」をまじまじと眺めるところを思えば、辰巳の芸妓にとっても刺青は「事件」であったにちがいない。
これまでの「刺青」論において、芸妓が娘に託したこの「手紙」について、触れられたことは寡聞の故か知らない。小林秀雄が「自然主義の蒼白な肌に芳烈絢爛な刺青をほどこした」(「谷崎潤一郎論」昭和六年四月「中央公論」)といい、三島由紀夫が「灰色の自然主義文学を背景にして、黒い曇天を背景にして咲き誇る絢爛たる牡丹の美を開顕した」(『豪華版日本文学全集』十二巻解説昭和四十一年十月河出書房新社)と、装飾的に言い換えたように華やかな「刺青」の物語は、清吉の「快楽と宿願」達成の一点に絞られて展開する。刺青師清吉が長年探しあぐねた理想の女との邂合(*1)によって「宿願」を果たす過程、さらに芸術家谷崎潤一郎誕生を暗示する女郎蜘蛛の完成(*2)の前に、その機縁を作った女の存在は、「メムフィスの民」の住むというナイル河岸に比すべき窓の外の美しい江戸大川の対岸風景に似て、手紙もまたその舞台装置の一部になっているのではなかろうか。
明治四十年代から大正初期にかけては、永井荷風の明治四十一年「夜あるき」(八月)「ひとり旅」(九月)、翌年の「監獄署の裏」(三月)を嚆矢とし、日本の近代小説に手紙の手法が盛んに用いられた時代でもある。近松秋江「別れたる妻に送る手紙」(明治四十三年四〜七月)、夏目漱石「手紙」(明治四十四年六月)「心」(大正三年四月〜八月)、森鴎外「羽鳥千尋」(明治四十五年八月)「興津弥五右衛門の遺書」(大正元年)、野上彌生子による試み「曙の窓より」(明治四十五年四月)「手紙」(大正三年二月)などの一連のもの、有島武郎「平凡人の手紙」(大正六年七月)「小さき者へ」(大正七年一月)等がそれである。
谷崎潤一郎は、戦後間もないころ三つの書信で構成された「A夫人の手紙」(昭和二十一年秋稿昭和二十五年一月「中央公論」別冊)を書いている。それより遥か以前の明治末年、作家として出発期にあった谷崎潤一郎が手紙を小説に持ち込むことにどれほど意識的であったかはわからない。しかし、「□風」(明治四十四年十月「三田文学」)「秘密」(明治四十四年十一月「中央公論」)、「羹」(明治四十五年七月〜大正元年十一月「東京日日新聞」)「続悪魔」(大正二年一月「中央公論」)に挿入された手紙は魅力的である。本稿では「刺青」を取り上げ、遠景におかれたもう一人の「手紙」の女について考えてみようとするものである。
2
清吉は歌川流(「豊国国貞の風を慕つて」とある)の元浮世絵師で、刺青師に「堕落」しているという設定である(*3)。清吉の心には「人知らぬ快楽と宿願」が潜んでいるが、その「宿願」とは「光輝ある美女の肌を得て、それへ己れの魂を刺り込む」こと、である。「美女」は美しいだけではいけない。刺り込まれた清吉の「魂」に見合う女でなければならない。しかし、浮世絵師として「渡世」をするだけの腕がありながら、刺青師に「堕落」した経緯や、清吉の「魂」は具体的には説明されてはいない。
記述から清吉の人物像を推察すれば、刺青の針を受ける男たちに対しては、「苦しき呻き声」に「云い難き愉快を感じ」、その「無残な姿」を「冷ややかに眺めて」「快さそうに笑」う男である。女に対しては、「男の生き血」を吸い「そのむくろを蹈みつけ」、「犠牲の男」の苦しみを眺め、「凱歌」の声を聞きながら男を「肥料」にすることを「美」のうちに要求する人物である。麻睡剤を用いて娘の意識と肉体を麻痺させ「宿願」の刺青を果たすような刺青師は、「画工」としての「良心と鋭敏」を除けば、立派な「悪」である。
注意すべき点は、清吉の「快楽」は男の苦しみを見ることにあり、「宿願」は、男を苦しめる残忍な女を自分の手で創り出すことにある。残忍な女とは、野口武彦(『谷崎潤一郎論』一九七三年八月中央公論社)が正しく指摘するように、「歌舞伎」(*4)や「草双紙」(*5)に描かれる次のような女である。
『刺青』の冒頭に列挙されるのは、女定九郎、女自雷也、女鳴神などの「美しい強者」たちであり、『四季』(昭和三十七年)で回想されるのは四代目沢村源之助が扮する『斬られお富』の夢魔的にまで凄惨な殺し場である。いずれのヒロインも残酷で畏怖すべき、いわばメデューサ的戦慄をもって男の嗜虐的快感をそそりたてる女たちであって、そのエッセンスは(中略)「『ざまを見やがれ』と云ひながら立つて居る』(『少年』)という絵双紙のイメージのうちに完璧に圧縮されている。
清吉は「紙」の代わりに「皮膚」を選び(*6)、「奇警な構図と妖艶な線」に腕をふるう刺青師に「堕落」する。この「堕落」という言葉の背後には、例えば小説を書こうとして「頭」に「空虚」より外に出て来なくなった「饒太郎」(「饒太郎」大正三年九月「中央公論」)に記述された次のような一節を思い起こしてみるのがいい。
彼と雖も芸術家である以上は、何等かの『美』と云ふものが全然実感的な、官能的な世界にのみ限られている為めに、小説の上で其の美を想像するよりも、生活に於いて其の美の実体を味ふ方が、彼に取つて余計有意味な仕事となつて居る。(中略)彼には小説よりも絵画の方が、絵画よりも彫刻の方が、彫刻の方よりも演劇の方が、演劇よりも舞台に現はれる俳優の肉体自身の方が、一層痛切な美を齎すのである。此の傾向がだんだん著しくなつた結果、今日彼の小説に書かうとする事柄は、単純なエロチシズム以外に、もはやなくなった。
「快楽と宿願」が清吉を「堕落」に導いたか、あるいはその逆か、「刺青」には明確に書かれていない。谷崎自身、自伝的小説「『異端者の悲しみ』はしがき」(大正六年七月「中央公論」)において「此の小説は、我等親子が不幸の絶頂に沈淪して居た七八年前の一時期を材料にしたものである。あの時分は、父も母も予自身も、人生に対して殆ど絶望的な心を抱いて居た」と語るように、強い精神衰弱を発症した放蕩生活の渦中に「刺青」は誕生している(*7)。作家の実生活の悲惨=堕落生活と「刺青」の誕生、清吉の刺青師への堕落と「光輝ある美女」との出会い、そして「女郎蜘蛛」の完成は重なっているわけである。その仲立ちに立っているのが「辰巳の芸妓」である。
「堕落」には、禁制の刺青を扱う者という意味と、経済的な事情も含まれる。「刺青師が刺青なす工銀」(『明治社会事彙』明治四十一年十二月 経済雑誌社)は次のように記す。
大抵尋常の人なれば一日金一分。駕籠舁きなれば八百文を常法とす。しかして刺青する人は。日々刺青師の家に通ふなり。又寄宿して刺青するものもあり。一人の刺青は大抵日数百日を費すなり。即ち二十五両の工銀にして駕籠かき八両の工銀なり。(按ずるに此頃は拾両一資本と称へ。拾両の金円を有すれば一商売の資本となり。一家二三人の生計をなして猶余りありし。然るに一人の刺青に二十五両を要する。実に莫大の費といふべし。されど弊風の走るところ。禁ずること能はず。往々家産を傾けて刺青をなし。腕をまくりて。財産は此の如く一身に付し去れりなど。誇りて人にに示す。人またこれを見て愉快とせり)
「駕籠舁」「鳶の者」は収入に関わるから競って刺青を彫った。刺青師が「賤業」であっても、その気になれば法外な現金収入を手に入れることができたわけである。「一切の構図と費用とを彼の望むがまま」にした清吉が、腕を頼みの経済力によって「辰巳の芸妓」と遊興することは可能である(*8)。
3
谷崎潤一郎自身が「刺青」について語った「創作余談」(昭和三十一年八月「別冊文芸春秋」)によれば、当初の「刺青」は現代を舞台に設定したもっと「長い物」であったという。
あれ(「刺青」)も実は発表したものは徳川時代に持つて行つてゐるが、最初は徳川時代に持つていかないで現代のことにして書いた。然ももつと長い物であつた。それを何処へ持つて行つて見て貰はうかなと思ひ、泉鏡花の所へ持つて行かうと思つたことがある。それを短く縮めて発表したのが『新思潮』の第三号。原稿が出来たのは「誕生」よりも「刺青」の方が先だが、最初現代風に書いてあつたのを徳川時代にもつて行かうといふので一寸待つているうちに、創刊号に取り敢へず何か出さなければならないというふので「誕生」を出したわけである。徳川時代に持つて行つたのは、現代ではどうも作品の上で具合が悪かつたからだ。
現代では「具合が悪かつた」のは、明治政府が「刺青」をたび重ねて禁じていたためであろうか(*9)。「REAL CONVERSATION」(「新思潮」第三号)には、発禁を恐れてあらかじめ語句の訂正を依頼したことが話題になり、「『新思潮』の人々」(大正七年一月「文章倶楽部」巻末大付録)には「伝手を以て警視庁の検閲係に内見して貰つた」ことが書き記されている。
谷崎の刺青についての調査は十分で(*10)、細江光によって、その出典の一つ『日本社会事彙』(明治四十一年十二月経済雑誌社)が明らかにされ、西澤正彦(*11)に『類聚近世風俗誌』(明治四十一年十一月二十五日原題は「守貞漫稿」)、塩崎文雄(*12)に松浦静山『甲子夜話』(文政四年十一月十七日起稿)などの刺青の記述のある文献が指摘されてもいる。しかし、「刺青」にある「蝋燭の芯を掻き立て」(*13)、清吉が二階座敷を仕事場にすること(*14)に関して、これらに記載は見えない。日露戦争後明治四十年代から関口亀次郎(紺三)によって「神田彫勇会」(*15)が再興されているので、谷崎は実際に刺青師の仕事場を見聞した可能性もある。
いずれにしても、「刺青」を「現代=明治末年」に設定して描こうとすれば、明治四十年代にその下地は整っていたわけである。発禁を恐れなければ、時代は江戸時代である必要はない。
細江光「『象』・『刺青』の典拠について」(一九九二年三月「甲南国文」39)、塩崎文雄「<テクスト評釈>『刺青』」(一九九三年十二月「国文学」)が指摘するように、「女定九郎」「女自雷也」「女鳴神」は、江戸時代よりむしろ明治期に頻繁に上演されている。谷崎自身その初期の作品に「草双紙の影響は非常にあります」(座談会「谷崎文学の神髄」(昭和三十一年三月伊藤整・武田泰淳・三島由紀夫・十返肇『文芸』臨時増刊 )と述べる「草双紙」にしても、美しい女が刺青の肌を見せて刃物を振りかざすような、毒婦ものの多くは明治期に出版されている。
綿谷雪『近世悪女奇聞』(昭和五十四年五月青蛙房)には、伊東橋塘(専三)『鳴渡神雷お新』(明治十六年五月東京滑稽堂)、仮名垣魯文『高橋お伝夜叉物語』(守川周重画明治十二年二月金松堂)はじめ十七人の「毒婦」を主人公にした草双紙が紹介され一種壮観であるが、このうち「雷お新」は総身絢爛たる刺青で彩られ、高知で一と謳われた美貌を武器に、盗み恐喝を重ね、名士も毒牙にかけたという。

4
言うまでもなく「刺青」は「嘘」の話である。清吉が、女郎蜘蛛を刺り始めたのは昼頃、仕上がったのは翌朝の暁である。玉村晴朗によれば、このように刺青を刺り続けたら「いくら麻睡がかけてあっても、まず死んでしまう」(『文身百姿』)という。
「刺青」は、娘が清吉の命をもらった代わりに、女郎蜘蛛を背中に負って生きる、いうならば怪奇変身譚である。「長い月日を色里に暮らして、幾十人の男の魂を弄んだ年増のやうに物凄く整つた」顔を持ちながら「臆病な心」を持つ小娘が、背中に女郎蜘蛛の刺青を入れた後は、その容貌にふさわしい男の命を肥料にする「女」に変貌する。それは、単に刺青の針を耐えたことによる自信、容貌の変化が人格に影響を与えた、という変化とは異なっている。
麻睡剤から覚めた娘の背中の女郎蜘蛛は、肩息に「生けるがごとく蠕動し」、瞳は「夕月の光を増すやうに、だんだんと輝いて男の顔に照」る。湯から上がれば、娘はすでに剣のような瞳を輝かす「女」となり「……お前さんは真先に私の肥料になつたんだねえ」と言うその瞳に映るのは、清吉の運命を暗示する『肥料』の画面である(*16)。瞳が「夕月」となり、八本の足を延ばして「旭日」となって輝く女郎蜘蛛こそが、清吉の「魂」であり「命」が融け込んだ「魔性」であろう。
谷崎潤一郎は、戯曲「誕生」によって世に出たが、掲載された第二次「新思潮」創刊号(明治四十三年九月)には、谷崎の評論「『門』を評す」が掲げられている。谷崎の矛先は漱石の筆力を讃えながら、鋭くその「道徳」の「嘘」を追う。谷崎は、宗助とお米が受けている罰、「貧」「病気」「流産」を指して、「世の中の因果応報と云ふものは、案外もっとルーズな、ふしだらなもの」で、「世間はもっとアイロニカルな事実に富むでいる」と言う。二人の生活は姦通の復讐を受けながらロマンチツクであることを指弾し、詰め寄る。
自己を偽らざらむが為めにあらゆる物を犠牲にして、真の恋に生きむとして峻厳なる代助の性格は、恋のさめたる女を抱いて、再びもとのやうな、或はそれよりも更に絶望なヂレンマに陥る事がありはすまいか。其の時々にこそ二人の姦通者は真の報復を受くべきである。若し「それから」が「門」に描かれたやうな発展の径路を取つたとしたらならば其れは作者に取つても代助に取つても甚好都合な次第であると云はねばならぬ。(中略)先生(漱石=注八木)は「恋は斯あり」と云ふ事を示さないで「恋は斯くあるべし」と云ふ事を教えて居られる。(中略)我々もならう事なら宗助 のやうな恋に依つて、落ち付きのある一生を送りたいと思ふ。けれども其れは今日の青年に取つては到底空想にすぎないであらう。
明治四十三年五月十八日、谷崎は大貫雪之助に宛てて一通の手紙を出している。それは新しく「燃え立つ」恋を打ち明けた手紙で、五年前に出会った恋人(*17)の「可憐な清浄な女の真心を欺」くものである。
新しい恋人は、「所帯の持ちの悪いことも、教育のない事も、節操の観念の乏しいことも」これまでの恋人と同日の論ではない。まして「姉は油断のならぬ淫婦」であるとしたうえで、次のように続ける。
五年前の夏の夜に、箱根と手を握り合つて銀坐を散歩した時、あくる年の五月に「恋しき恋しき谷崎様へ」と書いた手紙を受け取つた時、それ以来は柳橋に、天神に、洲崎に、浅草に、助川に、小田原に、幾人の女の肌にふれてもつひぞ味はず、忘れ切つて居た此のおのゝきにかくしても亦出会しやうとは!
なつかしい初夏が近づいた。僕と箱根との恋は四年前の初夏に始まつた。それから年々六月の来る毎に、若葉の香を嗅いでは昔の夢を見て居た。今年の初夏には第二の恋が生まれたのだ。新緑の若葉の色を見、紺の香高き久留米絣の単衣を着換へて、新しき恋のおのゝきを味ふ嬉しさ。
僕はまだ其の人にうち明けない。うちあけたら其の人は僕を愛してくれるかどうか、今の処全くわからない。
「箱根」とは、谷崎潤一郎が家庭教師を兼ねて寄宿していた北村家に小間使いとして入っていた穂積フクである。谷崎はこの女性に宛てた恋文の発覚により、北村家を出た。谷崎はこの古い恋を続けながら燃え立つ恋に苦しむ。
たとへ愛してくれずとも僕の妻にさへなつてくれゝばよい。僕は其の人のまごゝろを必ずしも要求しない。僕は其の人に欺かれてもよい、弄ばれてもよい、殺されてもよい。唯何等かの関係で密接して居たい。其の人の夫となれずば、甘んじて其の狗、其の人の馬、其の人の豚となろう。
反自然主義を掲げた谷崎潤一郎の作家としての出発はまた、漱石なるもの、すなわち「一般読者」に配慮し「かくあるべし」とする作家への挑戦とともにある。
5
清吉は刺青を施す前に、娘に二つの巻物を見せる。一つは淫楽と残虐の限りを尽くした古代中国殷の紂王の寵妃「末喜」(*18)を描いたもの、もう一つは娘の「未来を絵に表した」という「肥料」である。娘は、なよやかな体を匂欄に持たせて「犠牲の男」を眺める妃の風情に「隠れたる真の『己』を見い出し」青ざめる。娘の未来を描いたという『肥料』を見て「恐ろしい誘惑を避けるが如く、画面に背いて畳の上へ突つ伏」す。
それにしても、娘をこれほど恐怖させる美しくもおぞましい絵とは、いかなるものか。若き谷崎潤一郎の筆は、麗らかな「花園の春の景色」に重ねてそれを描写しない。
「刺青」は、当初現代を舞台に設定したもっと「長い物」であったことは先に述べたが、時代を現代に設定したとすれば、「刺青」が書かれた年は明治四十三年ということになる(*19)。「堕落」した刺青師清吉が娘に巻物を見せたのは、下関日清講和条約の年明治二十八年四月七日から十五年、ポーツマス日露講和条約の年明治三十八年九月五日から「足かけ五年目」の春ということになる。大正三年八月、日本はドイツに戦線を布告、第一次世界大戦に参戦する。桜の幹へ身を倚たせ、殺戮で犠牲となった男を、その足下に見つめている美しくも恐ろしい女の絵こそ、日本そのものではなかったか。「和蘭医から貰つた麻睡剤」は、日本が日本を一時忘れるための妙薬。美女が魔性を抱え込むときにどうしてもなくてはならないものだった。こう考え、そこに時代背景をみることも
許されるのではなかろうか。
「この絵は刺青と一緒にお前にやるから、其れを持つてもう帰るがいゝ」
かう云つて清吉は巻物を女の前にさし置いた。
娘を帰す清吉は敗北者だが、その言葉は冷静である。帰った娘はいよいよ複雑な関係の中に身を置く。清吉が馴染みを重ねた「辰巳の芸妓」は、「愚」という貴い徳の時代を白い羽織りの裏に残したまま、遠景に去るだろう。読まれても、その役目を果たさなかった「手紙」は、若い清吉の骸のかたわらを舞う。
[註]
- 森安理文「『刺青』論−その劇的享楽的について−」(一九七四年十一月「国学院雑誌」)は、「『刺青』の全体から享ける娘の華麗な肉体」は、「古風な色里暮らしの中に設定し」たにもかかわらず「谷崎が潜在的に志向する西洋風な女の肉体を髣髴させている」とのべる。
- 永栄啓伸「谷崎『刺青』覚書」(一九七七年三月「解釈」)は、清吉の魂が刺青の内に吸い取られ、彼の理想の女の肉体と実際に合体しているとする。
佐々木寛「『刺青』読みかへの試み」(一九八一年十一月「文芸と批評」5巻6号)。刺青師「清吉」は、谷崎潤一郎の分身であるよりも、中学時代の恩師稲葉清吉であり、「背に巨大な女郎蜘蛛の刺青を彫り込まれる娘の側に作者の強い自己投影を認めたいと思う」と述べる。
西澤正彦「『刺青』論−清吉の堕落劇」(紅野敏郎編『論考谷崎潤一郎』桜楓社一九八〇年五月)は、河竹黙阿弥作「十六夜清心」(「小袖曽我薊色縫」安政六年二月江戸市村座初演)の「清心」、後の「鬼薊清吉」と重ねて読む。「十六夜清心」は明治三十二年八月歌舞伎座、明治三十六年二月宮戸座、明治四十二年一月歌舞伎座で上演されている(鬼薊清吉はいずれも市村羽左衛門)。「『新思潮』の人々」(「文壇三十年物語」大正七年「文章倶楽部」巻末大付録)には、「今清心」とよばれた「潤一郎の蓬頭」の逸話がある。
- 西澤正彦「『刺青』論 −清吉の堕落劇−」(『論考 谷崎潤一郎』紅野敏郎篇一九八〇年五月 桜楓社)。谷崎は「清吉の堕落劇という下降意識と宿願の女性の前に排跪して幸福な恍惚感に浸ろうとする上昇志向との狭間に自らの進むべき道を求め」るとする。西澤は、この浮世絵師のモデルを月岡芳年とする。
- 「幼少時代」(昭和三十年四月〜三十一年三月「文芸春秋」)には「お神楽と茶」「団十郎、五代目菊五郎、七世団蔵、その他の思ひ出」に母や叔父とともに観劇した芝居の記憶と印象が鮮明に記されている。
- 岩佐壮四郎「『刺青』−「宿命の女」の誕生−」(一九八四年「紀要」43号関東学院大学)は、明治三十三年、上下二編の和綴じ木版本(続帝国文庫)として出版された草双紙『白縫譚』(嘉永二年〜明治十六年 柳下亭種員、柳亭種彦、柳水亭種清作三代歌川豊国)と「刺青」との関わりを指摘している。
「続悪魔」の主人公佐伯の愛読書の講釈本「佐竹騒動妲己のお百」の表紙は、「毒々しい程青い波の色に取り巻かれて、今や将に水面へ触れんとする女の足の裏の曲線、妖婦らしい目の表情、手頸襟頸など大した不自然もなく描かれて居る。其れを見て居ると、此の本の内容──さまざまの込み入つた、残酷な話の筋が想像されて、自然と魂をそゝられる。」と、娘の描写に類似した表現がある。
- 細江光(「『象』・『刺青』の典拠について」)は、清吉のこの「肉体」の選択について、君島一郎の『朶寮一番室−谷崎潤一郎と一高寮友たち−』(一九六七年十二月時事通信社)に記された「どんな積りでこんなものを書くのかと彼にたずねたことがあった。すると彼は、俺は実際の生活が大事なんで、それが俺の芸術なんだ。好きな為たい放題の生活をしたいんだが、それにはもと手がいる。金がないと出来ないから書いて、そしてそのたしにする。」という意味のことを谷崎が言ったという文を引き、「背徳的な享楽生活の実践」執着したことは、人間として芸術家としても堕落ではないかという後ろめたさを感じていたのではないかとする。
- 谷崎は精神衰弱によって明治四十二年日立市(助川)快楽園別荘に転地。明治四十五年四月〜五月の京都旅行中に再び襲われたことは「『刺青』『少年』など 創作余談(その二)」(一九五五年年十月二十八日「別冊文芸春秋」54号)に谷崎自身が語っている。竹盛天雄は谷崎潤一郎の放蕩の終焉を「異端者の悲しみ」におく(「蕩児の帰還−一九一〇年代の谷崎文学一斑−」一九七五年十月「日本近代文学」第22集)。
- 藤懸靜也『浮世絵』(一九二四年五月雄山閣)によれば、豊国(一七六九〜一八二五)は役者絵で評判を集め、国貞(一七八六〜一八六四)が三代豊国を襲った天保頃から、歌川流は一流を独占、競争心を失った浮世絵界は不振に陥ったという。
国芳(一七九七〜一八六一)は、三代豊国の勢力下で苦しみ、勇壮な武者絵によって新機軸を開き、月岡芳年(一八三九〜一八九二)から、水野年方、鏑木清方へとつながる浮世絵の命脈を築く。浮世絵師らが密かに刺青の下絵を描いていたことは広く知られている。
玉林晴朗は、画料が思うように得られない浮世絵師国芳が、兄弟子の国貞が「芸者末社」に囲まれて船中で豪遊しているのに出逢い、「自分の生活の苦しさに引換えて」心穏やかでなく、発奮し毎日画法を練ったという逸話を記している。(『分身百姿』 一九五六年十月 文川堂書房)
- 「違式□違条例」(明治五年十一月)、「刑法」(明治十三年七月)、「警察犯処罰令」(明治四十一年九月)において刺青を禁じた。明治二十七年七月二十七日の「都新聞」は浅草座で「仏蘭西土産三人兄弟」出演中の川上音二郎の全身に無数の鼠の刺青が客の侠客に見破られ「川上刺繍ある事を大いに恥じ」た記事が見える。西郷従道は背中から腹部一面に緋桜が舞う中に魯知深大和尚が六十二斤の鉄杖を振り回している見事な刺青があったという(『近世悪女奇聞』)。名だたる政府名士の肌にあるからか、禁じてもなお改まらず、「東京朝日新聞」(「入墨師岩田五助、アメリカへ」明治三十一年一月二十七日)、「国民新聞」(「日本人のいれずみ施術流行」明治三十四年三月二十三日)には、海外での日本の刺青の人気が欧州皇族、米国女優などの間に高まる一方であることが報じられている。
- 伊藤甲子之助「谷崎潤一郎と私」(一九七八年三月『谷崎潤一郎全集』月報十七)で、谷崎が刺青についての博識を披露した思い出を記している。
- 註3参照。
- 塩崎文雄「<テクスト評釈>『刺青』」(一九九三年十二月「国文学」学燈社)。
- 山田一廣『刺青師一代−大和田光明とその世界』(一九八九年十二月十日 神奈川新聞社)に刺青を依頼する者は「ろうそく一本と半紙を一帖持参するのがしきたりとなっていて、ろうそくが燃え尽きる間に一回分の仕事が終了した」とある。
- 玉林晴朗は「多くの文身師の家は下が居間で仕事場は二階になつている」と記す。(『文身百姿』)
- 「神田彫勇会」設立は、明治三十五年関口亀次郎(紺三)会長。明治四十五年に「江戸彫勇会」と改められた。玉村は「江戸時代の文身会が奇巧の競争であつたのに反し明治後東京に開催された文身会は真面目な図柄を競べ合ふ正道の会であつた」と記す。(『文身百姿』)。
- 「刺青」が胡蝶本に収録された際、初出結末近く「〜瞳を輝かした。」と「その耳には〜」の間にあった「其の瞳には『肥料』の画面が映つていた。」の一文が削除された。
- 野村尚吾『伝記 谷崎潤一郎』(一九七二年五月六興出版)に、福子をめぐって複雑な経緯のあったことが示されている。
谷崎自身は、「高等学校へ這つた時分に、或る純潔な無邪気な処女と知り合つて、互に愛し合つた。此れがほんたうの初恋と云ふべきものであつたろう。彼の女は今から六七年前に心臓を病んで、時分の故郷の或る温泉で死んでしまつた。彼の女の帯びて居た背負上げの中には、私の写真と私から送つた文殻とが入れてあつた筈であるが、臨終の時にどうなつやら分からない。さうして彼の女が私へ寄越した文殻は、未だに私の篋底にしまつてある。」(「私の初恋」「婦人公論」大正六年四月)と語る。
- 紂王の寵妃は「妲妃」。
- 江戸時代に時代を移す前の「原『刺青』」がいつ書かれたかを特定するのは難しい。谷崎が「刺青」の成立について述べたものは、「学校時代」(大正五年四月)、「『少年世界』へ論文」(大正六年五月)、「明治大正文学全集谷崎潤一郎篇解説」(昭和三年二月 河出書房)、「青春物語」(昭和七年九月〜昭和八年三月)、「創作余談」(昭和三十一年八月、十月)の五つである。佐々木寛が「『刺青』読みかへの試み」(「文芸と批評」一九八一年十一月)でいうように、「刺青」成立の時点は、谷崎自身が揺れていて特定できない。私見では、清吉が平清の前で娘の素足だけを見た「去年の六月ごろ」すなわち明治四十二年六月ごろではないかと推定する。
※尚、本文の引用は特に注記のないものは一九七二年版『谷崎潤一郎全集』によった。短編「刺青」については初出を参考にした。